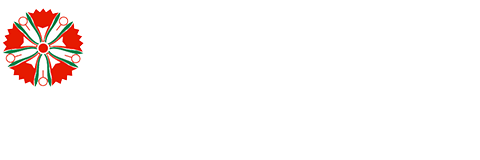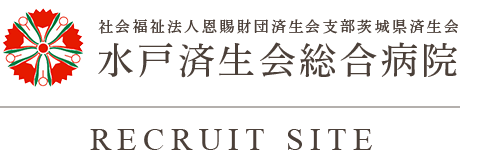臨床研修ブログ
- トップ
- 臨床研修ブログ
水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。
医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。
鑑別疾患のあげ方 その1
もう12月に入りました。
当院では今月から新しい科に
ローテーションした研修医も多く、
まだ落ち着かない様子ですね。
やはりローテーションすると、
慣れるまで2週間ほどかかります。
あせらず行きましょう。
さて、今日は鑑別疾患の挙げ方に
ついて紹介します。
鑑別疾患を思い浮かべながら
診療に当たらないと、すぐに
袋小路にハマっています。
例えば発熱患者はみんな肺炎か
尿路感染症、胸痛の患者はみんな
狭心症。腹痛の患者はみんな
便秘か胆石発作と診断してしまう・・・。
あなたも経験があるはずです。
編集長が勧める鑑別疾患の挙げ方は
2つあります。
一つ目は病因から攻める方法
有名な VINDICATE!!! + P
(ヴインディケイト+P)です。
二つ目は解剖学的に攻める方法です。
今回はVINDIVATE!!!+P
(ちなみに!!!にも意味があります)を
紹介します。
V:Vascular (血管系)
I:Infection (感染症)
N:Neoplasm (良性・悪性新生物)
D:Degenerative (変性疾患)
I:Intoxication (薬物・毒物中毒)
C:Congenital (先天性)
A:Auto-immune (自己免疫・膠原病)
T:Trauma (外傷)
E:Endocrinopathy (内分泌系)
!:Iatrogenic (医原性)
!:Idiopathic (特発性)
!:Inheritance (遺伝性)
P:Psychogenic (精神・心因性)
これは有名なティアニー先生が
紹介していたものですが、すごい
ところは全ての疾患が網羅されている
ところです。もともとティアニー先生が
病理学をやっていたので、こんな
アプローチに至ったと聞いたことが
あります。
原因が良く分からない、どこに
とっかかりを求めればいいのか
わからない、そんな時に呪文を
唱えながら鑑別を考えてみて下さい。
次回は解剖学的に攻める方法を
紹介します。
(編集長)

中学生の職場体験での一コマ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆病院見学に来ませんか?
どうやって研修病院を決めたらいいのか
分からない・・・。
それには病院見学をするのが一番です。
さらに直接研修医から話を聞くのがベストです。
実際に見学に行くと、想像以上に雰囲気が
違うことに気づくでしょう。
ぜひ冬休みを利用して、当院へ見学に
お越しください。あなたの目でリアルな
研修生活をのぞいてみて下さい。
病院見学や、その他のご質問・お問い合わせは
こちらからご連絡ください。
↓
http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html
◆感想やコメントはFacebookページから
お願いします!
↓
https://www.facebook.com/mitosaiseikai/
—–
なぜアメリカへ?
当院で初期研修を行い、引き続き
腎臓内科医として活躍中の郡司先生が、
3か月という短い期間でしたが
アメリカに留学してきました。
郡司先生は腎臓内科医のはずですが、
透析のシャント(=VA:Vascular access)
に精通しており、医師向けの講習会で
タスクフォースを務めるなど若手ながら
活躍中です。
そんな郡司先生が、VAのことをもっと
勉強するためにアメリカに行ってきました。
これから何回かに分けて郡司先生の
記事をアップしていきますが、
「コネなしからどうやってアメリカに
行けたのか?」とか、「アメリカの病院の
ホントのところ」など、面白い内容に
なっています!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私はミズーリ州セントルイスという
アメリカの真ん中あたりにある、
Washington University(WASU)に
Observershipという形で短期滞在
してきました。
日本では腎臓内科なのですが、こちらには
血液透析に必要なvascular access(VA)の
管理や手術などをみるために移植外科に
行きました。
学生のころから、海外にいくことなど
みじんも思っていなかった自分なので、
もちろん英語もYoutubeであいさつを
覚えるくらい。またUSMLEも持っていません。
ただ、自分の今後を考えたときに、
人生において海外を見る機会は今しか
ないのではないかと思ったのです。
日本の中での研鑽はこれからも
していかなければなりませんが、
海外に関しては、若いうちに見ておいた
方が自分にとっても良いのではないかと
考えました。そして、周囲の方々の
本当に理解のある応援もあり、
幸運にもWASUに行くことができました。
みなさんに本当に感謝しかありません。
VAの管理や手術成績などに関しては
日本が一番成績がよいとされています。
日本では中心静脈カテーテルを使用した
透析患者さんは世界と比べて少なく、
自己血管を使用したVAの比率も高く、
開存成績もよいのです。
しかし、アメリカは人工血管を使用した
VAや中心静脈カテーテルを使用した
VAが多く、社会的にも問題となり自己血管
によるVAを推奨する運動も行われている
くらいです。
このような状況なのに、なぜ自分は
アメリカを見てみたいと思ったのか
というと、今でも多くの外科系の医師は
アメリカに渡り研鑽を積まれる方がいる
ほど技術的には高いはずなのに、
なぜ開存成績なども含めて違いが
できてしまうのかを実際に見てみた
かったのです。
治療法、管理の仕方、スタッフ、患者の
理解度など、文献を見ているだけでは
伝わってこない実際を見てみたくなり
ました。
(郡司)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
次回はどうやってWASUに行くことに
なったのかを紹介します。
お楽しみに。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆病院見学に来ませんか?
どうやって研修病院を決めたらいいのか
分からない・・・。
それには病院見学をするのが一番です。
さらに直接研修医から話を聞くのがベストです。
実際に見学に行くと、想像以上に雰囲気が
違うことに気づくでしょう。
ぜひ冬休みを利用して、当院へ見学に
お越しください。あなたの目でリアルな
研修生活をのぞいてみて下さい。
病院見学や、その他のご質問・お問い合わせは
こちらからご連絡ください。
↓
http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html
◆感想やコメントはFacebookページから
お願いします!
↓
https://www.facebook.com/mitosaiseikai/
—–
HIVで知っておくべきこと・・・・松永先生のカンファより
少し前になってしまいましたが、
11月に松永先生の感染症カンファが
開催されました。今回のテーマは
「HIV」でした。
正直なところ当院でHIVに遭遇することは
非常に少ないです。でも、そのために
HIV治療の進歩についていけていない
ところがあります。
つまり我々が間違った理解している、
さらにそれに気づけていない危険が
あるのです。そういう点で松永先生
のレクチャーは重要です。
今回のレクチャーではHIVに関して
非専門家が知っておくべきことを
下記にまとめていただきました。
・HIV感染症は長期生存可能な疾患である
・良好にコントロールされているHIV感染者は
「免疫不全者」ではない
・良好にコントロールされているHIV感染者が
他者へHIVを感染させるリスクは非常に小さい
・不用意な治療中断は時に重大な結果を
もたらす
・一部の抗HIV薬は高度の薬物相互作用を
有する
・針刺し事故時に予防内服が有効である
・事故後の服薬開始はできるだけ早い方
が良い
・HIV感染症の専門家は決して相談を
嫌がらない
次回からこれらについて紹介していきます。
(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆病院見学に来ませんか?
どうやって研修病院を決めたらいいのか
分からない・・・。
それには病院見学をするのが一番です。
さらに直接研修医から話を聞くのがベストです。
実際に見学に行くと、想像以上に雰囲気が
違うことに気づくでしょう。
ぜひ冬休みを利用して、当院へ見学に
お越しください。あなたの目でリアルな
研修生活をのぞいてみて下さい。
病院見学や、その他のご質問・お問い合わせは
こちらからご連絡ください。
↓
http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html
◆感想やコメントはFacebookページから
お願いします!
↓
https://www.facebook.com/mitosaiseikai/
—–
ものの見方
編集長が先日読んだある記事に
こんなことが書いてありました。
「もしあなたが金槌しか持っていなければ
全ての問題は釘に見えるだろう」
(欲求階層説で有名な心理学者アブラハム・
マズロー)
何の事だか分からないかもしれませんが、
この言葉の意味はこんなことだと思います。
患者さんのことで、ある何かの問題を
解決する必要に迫られた時、
・消化器内科医は消化器内科の観点で
・消化器外科医は消化器外科の見地で
・循環器内科なら循環器内科の視点で
・看護師なら看護師の視点で
解決策を考えます。
つまり自分の持っている
「最も使いやすく手近な道具」を使って
解決する傾向が強い、ということです。
「自分が最も使いやすく手近な道具」を
使って問題を解決するということは、
もちろん悪いことではありません。
これは言い換えれば「長所発揮」であり、
強みを生かして課題や困難にチャレンジ
することは重要です。
しかし、当然ながら全ての問題が
「自分が最も使いやすく手近な道具」で
解決できる訳ではありません。
ところが、無意識に「手近な道具」を使って
考えているので、そのことに気づくのに
時間がかかります。
これを日常臨床に当てはめると、
患者さんの問題を解決するために
カンファレンスなどで他の診療科の先生と
議論をしたり、看護師さんやリハビリ、
ケースワーカーなどと患者さんについて
意見を出し合う場が必要ということです。
自分の診療科内だけでなく、他の診療科や
職種との議論は、自分が気づかなかった
アプローチを気づかせてくれる貴重な
機会なのです。
自分が手にしているのは、多くの場合
金槌である
ということを自覚しておかないと、
自分の知っている範囲でしか考えなくなり、
こじつけて解釈したりと、手段が目的化
してしまう危険性があります。
医学生や研修医のあなたの強みは、
診療科や職種を気にすることなく、
いろいろな人に相談できることです。
積極的に相談して、幅広い見方を出来る
ように、日々トレーニングしてください。
(編集長)

ERで救急隊から情報収集中
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆病院見学に来ませんか?
どうやって研修病院を決めたらいいのか
分からない・・・。
それには病院見学をするのが一番です。
さらに直接研修医から話を聞くのがベストです。
実際に見学に行くと、想像以上に雰囲気が
違うことに気づくでしょう。
ぜひ冬休みを利用して、当院へ見学に
お越しください。あなたの目でリアルな
研修生活をのぞいてみて下さい。
病院見学や、その他のご質問・お問い合わせは
こちらからご連絡ください。
↓
http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html
◆感想やコメントはFacebookページから
お願いします!
↓
https://www.facebook.com/mitosaiseikai/
—–
小児を診察はPATから・・・・第26回鑑別診断道場より
前回は小児の発熱で除外すべき
疾患を紹介しました。特に3か月未満の
小児の発熱は要注意です。
なぜなら、重症細菌感染症の頻度が
10~15%と高いにも関わらず、
発熱以外の症状がはっきりしない場合も多い。
そして身体所見では重症細菌感染症の
除外が困難だからです。
身体所見があまりあてにならないので
「何となく元気がない」が大事ですが、
それを評価するのが、
PAT(Periatric assessment triangle)です。
PATは「あれっ、なんだかこの子やばそう」
というのを
Appearance(外観・見かけ)
Work of Breathing(呼吸仕事量)
Circulation(循環・皮膚色)
で評価します。
Appearanceは「見た目が元気そう」
ということですが、具体的には
・筋緊張(ぐったりしていない、
手足を動かす)
・疎通性(呼ぶと振り向く、笑う)
・精神的安定(抱っこすると泣き止む)
・視線(視線を合わせる、おもちゃを
目で追いかける)
・会話/泣き声(声を出している)
これらが出来ていればOKと判断します。
Work of Breathingでは
・呼吸の速さ
・努力呼吸
・明らかな呼吸音の異常の有無
これらに注目します。
聴診器なしで呼吸音が聴こえたらヤバイし、
陥没呼吸(Retraction)が肋骨弓下や
胸骨下だけでなく、鎖骨上窩や胸骨上、
胸骨で見られたら重症です。
Circulation (to Skin)は
大人と違って、小児はバイタルサインが
循環動態を正確に反映しないうえ、
年齢によって正常値が異なるので
なかなか使いにくいのですが、
皮膚の状態が、全身の循環動態の
指標になります。
例えば皮膚の蒼白、チアノーゼ、
まだら模様は危ないサインです。
また、毛細血管再充満時間(Capillary
Refilling Time:CRT)も良く用いられます。
CRTは成人と異なり、小児では四肢を
心臓よりやや高い位置に持ち上げた
状態で、四肢の皮膚を押して素早く離し
ます。押した部分の皮膚の色が戻るまで
に何秒かかるかを確認し、正常なら2秒
以内に皮膚の色が元に戻ります。室温で
評価しないと間違えてしまいます。
ERを受診した小児を観察して、
笑顔が見られ、おもちゃに目を向ける
(Appearance)
頻呼吸や陥没呼吸なし
(Work of Breathing)
チアノーゼなし、末梢冷感なし
(Circulation)
ならば、PAT異常なしとして、現時点では
全身状態は良好と判断してください。
もちろんPATは3か月以上の小児でも、
使うことが出来ます。
(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆病院見学に来ませんか?
どうやって研修病院を決めたらいいのか
分からない・・・。
それには病院見学をするのが一番です。
さらに直接研修医から話を聞くのがベストです。
実際に見学に行くと、想像以上に雰囲気が
違うことに気づくでしょう。
ぜひ冬休みを利用して、当院へ見学に
お越しください。あなたの目でリアルな
研修生活をのぞいてみて下さい。
病院見学や、その他のご質問・お問い合わせは
こちらからご連絡ください。
↓
http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html
◆感想やコメントはFacebookページから
お願いします!
↓
https://www.facebook.com/mitosaiseikai/
—–
どう向き合うべきか?
臨床では患者さんが亡くなる
場面に遭遇します。そんな時、
あなたはどう受け止めて、
どう対処していますか?
そして残された家族にどういう
言葉をかけていますか?
少し前のことですが、ERでこんな
ことがありました。
50歳代の男性で、職場で突然の
心肺停止となり搬送されてきました。
結局のところCPRを行っても蘇生できず、
到着した家族はERで号泣していました。
こんな状況で、あなただったら残された
家族にどのように声をかけるでしょう?
考えてみて下さい。
↓
↓
編集長も正解を持っていないし、
いつもできている訳ではありませんが、
できることなら、少し落ち着いた
ところで、亡くなった患者さんが
どんな人だったのかを
家族に聞いてみると思います。
家族が亡くなった患者さんのことを
話すこと死を受け入れることにつながる
からです。でも、それにはある程度の
時間も必要なので現場では難しいことも
多くあります。
ある研修医は「研修を始める前は
人が死ぬのが怖くて、避けたかった。
でも、研修を始めてから、たとえ治療が
何もできない状況でも、患者さんや
家族と話をするだけで役に立っている
ことが分かった」という趣旨の話を
してくれました。
あなたもこれから何人も患者さんの
死と向き合います。それが我々の
重要な仕事の一つです。
一番よくないことは、どう対処したら
よいのか考えなくなること。
どう受け止めて、なんと声をかけるのが
良いのか、時々でも時間を取って
考えてみてください。
(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆病院見学に来ませんか?
どうやって研修病院を決めたらいいのか
分からない・・・。
それには病院見学をするのが一番です。
さらに直接研修医から話を聞くのがベストです。
実際に見学に行くと、想像以上に雰囲気が
違うことに気づくでしょう。
ぜひ冬休みを利用して、当院へ見学に
お越しください。あなたの目でリアルな
研修生活をのぞいてみて下さい。
病院見学や、その他のご質問・お問い合わせは
こちらからご連絡ください。
↓
http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html
◆感想やコメントはFacebookページから
お願いします!
↓
https://www.facebook.com/mitosaiseikai/
—–
3か月未満は要注意・・・第26回鑑別診断道場より
前回はFeverphobia(発熱恐怖症)を
紹介しました。
発熱を主訴にERを受診する小児の親は
とにかく「発熱自体が悪い」と考えて
しまっていることを、あなたも認識して
おく必要があります。
ではERで小児の発熱患者が受診したら
除外すべき疾患は何でしょう?
・3か月未満の発熱
・細菌性髄膜炎
・咽頭膿瘍、喉頭蓋炎
・菌血症
・尿路感染症
・肺炎
・心筋炎
・腹膜染
・化膿性関節炎(足を動かさない)
・(川崎病)
髄膜炎に関しては、ヒブや肺炎球菌
ワクチンの接種歴を必ず聞きましょう。
最近では接種しているので小児の
細菌性髄膜炎は激減しているそうです。
尿路感染症では、「尿が少ない」
「臭いがヘン」が疑うきっかけになります。
化膿性関節炎は「足を動かさない」
という訴えがヒントになります。
そして、3か月未満は要注意です。
なぜなら、重症細菌感染症の頻度が
10~15%あるとされています。
しかも、発熱以外の症状がはっきりしない
ことが多く、身体所見では除外が困難です。
良くわからないけど「何となく元気がない」
ことが唯一の危険なサインかもしれません。
実際のところ、
1か月未満は全例でFull sepsis work up、
1~3か月でも多くはSepsis work upが必要です。
(つまり血液培養や髄液検査など全部
やるということです)
さて、ここで出てきた「何となく元気がない」
これは小児診療で非常に重要なポイントです。
ただ何となくではなく、見るべきポイントがあり、
をこれをPAT(Periatric assessment triangle)
と呼んでいます。次回はこのPATを紹介します。
(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆第3回
小児救急はこわくない
~こども達の未来を救おう~
2018年12月15日(土)
当院で開催します!詳細はこちらから!!
↓
http://www.mito-saisei.jp/resident/mitoigakuseiseminar201812.html
定員まで、残り1名です!
お急ぎお申し込みください!
◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは
こちらからご連絡ください。
↓
http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html
◆感想やコメントは
Facebookページからお願いします!
↓
https://www.facebook.com/mitosaiseikai/
—–
Feverphobia(発熱恐怖症)・・・・第26回鑑別診断道場より
前回に引き続き、第26回
茨城県央レジデントセミナー
~鑑別診断道場~ からです。
レジデントセミナーでは、毎回
症例検討に加えて特別講演を
行っています。
今回の特別講演は水戸協同病院
腎臓内科の鈴木竜太郎先生に
「一歩先を行く当直小児科診療
〜小児も診られる内科当直医を目指して~」
のタイトルで話をしてもらいました。
なぜ腎臓内科医が小児科の話かと言うと
実は鈴木先生は当院で初期研修を
終えてから、お隣の県立こども病院で
研修を続け、腎臓病専門医を取得する
ために、今年度の9月までは当院で、
そして10月から水戸協同病院の
腎臓内科に所属しています。もとが
小児科医なので、当直での小児診療の
話をしてもらいました。
すぐに役立つ話が満載だったのですが、
今回はFeverphobia(発熱恐怖症)
を紹介します。
小児のER受診で最も多い主訴は発熱
ですが、親などの養育者の91%が、
発熱そのものが有害だと考えていた、
21%の養育者が発熱により脳に障害を来す、
14%の養育者は発熱により死を来す
と考えていたそうです。
Pediatrics 2001; 107: 1241-1246
確かにERでは発熱に対する不安を
聞きます。そして、その対処を詳しく
話しておかないと、いつまでも納得
してくれないことがあります。
同じデータでは、52%の養育者が1時間
ごとに熱を測っており、85%の親が、
子どもを起こしてでも解熱剤を与えていた
そうです。そして、人種や国籍にほとんど
差がみられなかったとのこと。
我々からすると、小児であっても高齢者
であっても、発熱していても他のバイタルが
安定していれば慌てませんよね。
でもERで小児の発熱を診察する時、
こういったFeverphobiaのことを踏まえて
発熱に対する恐怖感を取り除くように
丁寧に説明する必要がありそうです。
(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆病院見学に来ませんか?
どうやって研修病院を決めたらいいのか
分からない・・・。
それには病院見学をするのが一番です。
さらに直接研修医から話を聞くのがベストです。
実際に見学に行くと、想像以上に雰囲気が
違うことに気づくでしょう。
ぜひ冬休みを利用して、当院へ見学に
お越しください。あなたの目でリアルな
研修生活をのぞいてみて下さい。
病院見学や、その他のご質問・お問い合わせは
こちらからご連絡ください。
↓
http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html
◆感想やコメントはFacebookページから
お願いします!
↓
https://www.facebook.com/mitosaiseikai/
—–
バーネット先生のカンファ報告
水戸地区の研修病院では、毎年共同で
外国人医師を招聘し、研修医向けの
教育回診を行っています。今回も
医療コミュニケーションに造詣の深い
バーネット先生にお越しいただき、
各病院を回りながら教育回診を
開催しました。当院では2日間に
わたって症例検討とレクチャーを
行っていただきました。

医療コミュニケーションはあなたも
日常臨床で絶えず疑問や葛藤に遭遇
しているはずですが、何とかその場を
しのいで、そのままにしているのが
現状ではないでしょうか?
実際になかなか学ぶ機会が少ない
テーマですが、当院では研修医が
病棟やERなどで実際に経験した症例を
提示して、医学的な背景を踏まえつつ、
コミュニケーションの問題点について
みんなで議論したり、バーネット先生からの
レクチャーを受けるスタイルで行っています。
例えば2日目に行われた
「End of life care」
のセッションを紹介しましょう。
J1の田渕先生からの症例提示です。
症例は70歳台の男性、外傷性の
脳挫傷で気管切開をおいて
ベンチレーター管理になっており、
一言で言うと脳死ではないけど、
回復の見込みがない状態の患者です。
患者家族は意識が戻らないことを医師
からの説明を理解しているようですが、
一方で回復することを期待している言動も
見られています。
回復する見込みがない、かと言って
治療をやめるわけにはいかない。
このような場合、患者家族にはどう
アプローチしていけばいいのでしょう?
非常に難しい問題ですが、バーネット先生は
・家族にとって、患者はどんな人(夫、父、
兄弟)だったのか?
・もし患者が話せるとしたら、現在の状況を
何と言うだろうか?
これらを家族に質問して、患者や
家族のことをもっと理解し、信頼関係を
築くことを強調していました。
また提示した症例に限らず、
治癒の見込みのない患者に対する
緩和ケアを行う目標は、「症状を和らげ、
残りの生活の質を最大限にする」ことであり、
決して「ケアを控える」ことや「何もしない」
ことではなく、治療目標を変えることだ
と話していたことが印象的でした。
次回もバーネット先生のレクチャーから
紹介します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆病院見学に来ませんか?
どうやって研修病院を決めたらいいのか
分からない・・・。
それには病院見学をするのが一番です。
さらに直接研修医から話を聞くのがベストです。
実際に見学に行くと、想像以上に雰囲気が
違うことに気づくでしょう。
ぜひ冬休みを利用して、当院へ見学に
お越しください。あなたの目でリアルな
研修生活をのぞいてみて下さい。
病院見学や、その他のご質問・お問い合わせは
こちらからご連絡ください。
↓
http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html
◆感想やコメントはFacebookページから
お願いします!
↓
https://www.facebook.com/mitosaiseikai/
—–
【残りわずかです】 第3回水戸医学生‘小児科’セミナー
昨年開催して好評だった
水戸医学生‘小児科’セミナーの
参加申し込みを受け付け中です。
このセミナーの参加には
学年を問いません。
まだ、CBTも終えていなくても
大丈夫です。
ただし、1つだけ条件があります。
それは小児医療に関心があること。
このセミナーでは小児版のACLSである
PALS(Periatric Advanced Life Support)
を扱います。PALSは小児救急の基本
となるものです。
これを一部でも理解し、
身に付けることで
例えERに重症の子どもが
現れても、ビビらずに、
慌てずに対応できるように
なるはずです。
学年が低くても、
小児医療に関心のある
あなたにとって
決して無駄になることは
ありません。
特典付きの期間は終了しましたが、
まだ2名ほど空席があります。
どうぞ急いでお申し込み下さい。
お申し込みは、病院HPまたは
下記メールアドレスからお願いします。
どうぞお早目にお申し込みください!
メールはこちら
メールには
・お名前
・大学名および学年
・住所
・携帯電話(前日や当日の連絡先)
以上を必ずご記入ください。
お申し込み後は、自動返信メールが
送信されます。追って担当者から
ご連絡します。
開催要項
日時:
平成30年12月15日(土)
9:00~17:30(受付は8:30~)
場所:
水戸済生会総合病院、
茨城県立こども病院
対象:
小児医療に関心のある全国の医学生
12名
*学年は問いません
*定員になり次第締め切ります
費用:
無料
*昼食も準備いたします
*当院までの交通費はご負担ください
(編集長)

—–