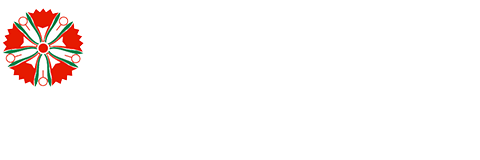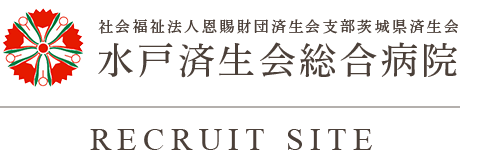臨床研修ブログ
水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。
医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。
全身のパラメータと局所のパラメータ・・・経過観察の2つの軸
70歳台の患者さんが尿路感染症の診断で入院しました。抗菌薬を開始していますが、3日たっても高熱が続いています。入院時の血液培養と尿培養からは、素直な大腸菌が検出され、抗菌薬は効いているはず・・・。
でも、熱が下がらないので、抗菌薬を代えた方がいいかも?なんて不安になることがありませんか? あなたはそんな時はどうしますか?
こんな時はまず、抗菌剤を変更する前に感染症治療が上手くいっているかの判断をする必要があります。でも、あなたは何を根拠に治療が上手くいっているかを判断していますか?
たいていの人は、発熱が続いているとか、WBCやCRPが下がらない、と答えてくれます。ホントにそうなのでしょうか??
WBCやCRP、PCTといった採血の項目は、確かに分かりやすく有用な指標ですが、その特徴と限界を理解しておく必要があります。
松永先生は「2つのパラメータ」をよく理解する必要性を強調しています。それは、「身体全体の総体を表すパラメータ(全身のパラメータ」と「感染局所の病態を表すパラメータ(局所のパラメータ)」です。
「全身のパラメータ」になりうるものには、体温、WBCやCRP、プロカルシトニンなどの炎症マーカー、そして敗血症性ショックの治療に用いられるノルアドレナリンの用量、インスリンの用量、乳酸値などがあります。
「局所のパラメータ」になるものには、感染局所の症状、徴候、グラム染色などの検査所見があります。
例えば、冒頭のような尿路感染症の患者さんなら、CVA叩打痛の程度や尿検査での白血球数や細菌数などが感染局所の指標になります。発熱という全身のパラメータが改善していなくとも、局所のパラメータが改善していれば、治療は上手く行っていると考えることができます。この患者さんで尿検査の所見が改善している(白血球が低下して、細菌が消失)ならば、抗菌薬を変更する必要はありません。実際のところ翌日の午後には解熱して、ご飯も全量食べていました。
「検査値を治しているんじゃない!患者を治しているんだ!」というのが、松永先生のメッセージです。
局所のパラメータの具体例を挙げると・・・、
【肺炎】
症状(咳、痰、呼吸困難感)、
徴候(呼吸数、呼吸器の設定、痰の量・質)
検査(血液ガス、喀痰のグラム染色)
【尿路感染】
症状(排尿困難、頻尿など)
徴候(腹部の圧痛、背部の叩打痛)
検査(尿中白血球数、尿グラム染色)
【蜂窩織炎】
症状(疼痛)、
徴候(発赤、腫脹、熱感、浸出液の量・質)
検査(浸出液のグラム染色)
【心内膜炎】
血液培養が検出されるまでの日数
血液培養の陰性化
感染症治療では発熱やCRPだけでなく、感染局所のパラメータに注目して、それを追いかけることが重要です。そして、これらのパラメータは診断する時点、治療を開始する時点で、経過を見る指標を決めていくことが大事です。発熱とCRPが改善しないと、つい抗菌薬を変更したくなりますが、まず局所のパラメータがどうなっているのかを評価してからです。惑わされないで頑張ってみてください。
(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?
どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
https://recruit-mito-saisei.jp/entry